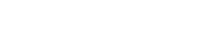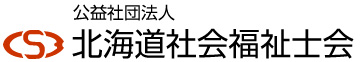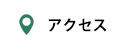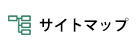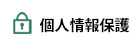トピックス
研修情報一覧
北海道福祉サービス第三者評価事業 2017年度評価調査者養成研修会
更新日付:2017.09.12
※申込数が開催定員に満たなかったため、研修会は開催中止となりました。
この研修会は、北海道福祉サービス第三者評価実施要綱第9 条第1 項第1 号に規定する評価調査者養成研修として、評価調査者の養成を図ることを目的とします。
日時
| 【1日目】 | 2017年9月30日(土)午前 9 時 30 分から午後 5 時 30 分まで |
|---|---|
| 【2日目】 | 2017年10月1日(日)午前 9 時 30 分から午後 5 時 30 分まで |
| 【3日目】 | 2017年10月2日(月)~11月3日(金・祝)のうちの1日(10:00~17:00) |
| 【4日目】 | 2017年11月4日(土)午前 9 時 30 分から午後 5 時 30 分まで |
会場
札幌市社会福祉総合センター4階大研修室など(1 日目、2 日目及び 4 日目) (札幌市中央区大通西 19 丁目(地下鉄東西線「西 18 丁目」下車)) 分野別現場実習(3 日目)は北海道内の実習協力施設で実施受講申込の方法
(1)申込期限(期限までに必着)
2017 年 9 月22日(金) ※ 期日までに申込みがない場合は、いかなる理由があっても、受講することはできません。(2)申込方法
①申込書に必要事項を記入の上、②顔写真(カラー・縦 3cm×横 2.5cm)と、③受講資格要件を証明する書類(「勤務証明書」・「資格証」の写し。詳細は別表2を参照のこと)を添付して提出してください。 ※ 写真は携帯版評価調査者証に使用します。写真の裏に氏名を必ず記載して下さい。過去に継続研修を受講された方についても写真は必要です(評価調査者証には、「組織」「福祉」「総合」の区分、「保育・障がい・高齢・救護」の区分を新たに印字します。)。2017年度社会福祉士実習指導者講習会【締切延長】
更新日付:2017.09.12
※申込締切を延長しておりますので受講希望の方はお問い合わせください。
「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、社会福祉士養成カリキュラムが改訂され、相談援助実習を行う実習指導者の要件として、実習指導者を養成するための講習会の受講が義務付けられ2012年4月から完全施行されました。下記の日程で、2017年度社会福祉士実習指導者講習会を開催しますのでご案内します。本講習会は実習指導者の要件を満たす講習会として厚生労働省に届出られたものです。
| 日 程 | 2017年10月 14日(土)~10月 15日(日) |
|---|---|
| 会 場 | 学校法人西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校 B棟3階 講堂 〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5 アクセス:地下鉄東西線 「西11丁目」下車し徒歩約5分 |
| 定 員 | 100名 |
自己評価研修会(社会的養護関係施設編)
更新日付:2017.08.06
※申込期限を過ぎても受付可能ですのでお問い合わせください。
社会的養護関係施設は、平成 24 年度から毎年の自己評価及び3年間に1回の第三者評価の受審が義務化され、今年は 2 クール目の最終年となりますが、第三者評価の受審については、毎年の自己評価をいかに生かすかが重要と考えます。
施設の職員の皆さんと第三者評価調査者が学び合うことで、毎年の自己評価が充実したものとなるよう、本研修会を以下のとおり開催いたします。
| 日時 | 2017 年(平成 29 年)8 月 19 日(土) 10:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 札幌市社会福祉総合センター 4階 大会議室 (札幌市中央区大通西 19 丁目 1-1) ・地下鉄東西線「西 18 丁目駅」1 番出口から徒歩 3 分 ・JR 北海道バス・中央バス「北 1 条西 20 丁目」バス停下車徒歩 3 分 |
| 受講対象者 | ・ 児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生 活支援施設の職員及び福祉サービス第三者評価事業評価調査者 ・ 定員100名(定員になり次第締め切ります) |
| 受講料 | 5,000 円 |
| 受講申込の方法 | (1) 申込期限 2017 年(平成 29 年)8 月 7 日(月) (2) 申込方法 受講料は、前払いとなります。振込票控えを申込書に添付し、FAX又は郵 送でお申込ください。振込用紙は郵便局に備え付けの「青色 振込取扱票」 (振込手数料 各自負担)をご使用ください。 |
ソーシャルワーカーデー2017in北海道“海の日カフェ”
更新日付:2017.07.12
~人を支え 自らを知り 社会を変える専門職から、いま伝えたいこと~
社会福祉の現場では、いろいろ悩みながらも、多くの人を支え、やりがいを感じて働く職員がたくさんいます。そういった存在やソーシャルワーカー等がどんな職業かを今後の進路を考える高校生等に知ってもらうために企画しました。
今回開催する“海の日カフェ”では、参加者が小グループごとに飲み物やお菓子を楽しみながら、福祉の最前線で働く若手ソーシャルワーカー、ケアワーカー数名から『福祉現場のリアルと魅力』を話してもらいます。
| 日時 | 7月17日(月・祝)13時00分~15時 |
|---|---|
| 場所 | かでる2・7 520研修室 |
| 対象 | 高校生(中学生も可)、保護者、教員 |
| 申込 | 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、郵送・FAX・メールにてお申込み下さい。 |
十勝地区支部研修会のご案内
更新日付:2017.07.06
北海道社会福祉士会十勝地区支部 罪に問われた高齢、障がい者に対する支援に関する研修会
罪を犯した高齢者・障がい者の中には、必要な福祉的支援に結びつくことができず生きづらさを抱えた人達、疾病や障がいの十分な理解がされないまま罪に問われる人達、その環境から逃れることができず何度も罪を繰り返す人達、そのような人達が少なからずいるとされている。 誰もが住み慣れた地域でその人らしく生きていくために、司法と福祉が連携し、それぞれが自分のマチのこととして取組んでいくことが求められている。 今回の研修会では、刑務所、相談支援機関から実際に関わった事例や活動内容を報告いただき、地域の現状を把握するとともに、十勝において求められる司法と福祉の連携のあり方について協議する機会とする。| 日 時 | 平成29年7月27日(木) 19時00分~20時30分 |
|---|---|
| 場 所 | 帯広市グリーンプラザ BC会議室 |
| 参 集 | 社会福祉士、弁護士、司法書士等、司法と福祉の連携に関心のある方 |
| 定 員 | 20名程度 |
| 申 込 | 資料や会場準備の都合上、メールにてお申込み下さい。 |
| 申込締切 | 平成29年7月24日(月) |
| 申込・問合先 | 北海道社会福祉士会十勝地区支部 司法連携部会 長村 麻子 Eメール:an_05_78@yahoo.co.jp |
道央地区支部 会員サロンのご案内
更新日付:2017.07.05
こんにちは♪道央地区支部が開催する会員サロンをご案内します。
会員サロンは、会員等が定期的に集まり、資質向上、意見交換を行うことで社会福祉士としてのアイデンティティを確認するとともに、参加者が交流の機会を通じて、分野を超えたネックワークを広げることを目的にします。
今回のテーマは、「災害支援」。参加をお待ちしています。
| 日 時 | 9月6日(水)18時30分~20時の予定 |
|---|---|
| 会 場 | 札幌市社会福祉総合センター「視聴覚室」4階 (札幌市中央区大通西19丁目 地下鉄東西線「西18丁目」下車徒歩5分) |
| テーマ | 「社会福祉士による災害支援活動の実際-支援を受け入れた立場から-」 |
| 内 容 | 釜石市地域包括支援センター社会福祉士が東日本大震災の体験談を語るDVDを鑑賞します。 |
| 参加費 | 本会会員は無料。非会員は500円(当日、受付にていただきます。) |
| 定 員 | 50名(お早めにお申し込みください。) |
| 参加申込 | 9月1日(金)までにFAX(011-688-6878)にて参加申込書をご送付ください。 |
| 次回開催 | 12月1日(金)になります。改めてご案内いたします。 |
虐待防止研修会 案内
更新日付:2017.07.04
※定員に達しましたので受付を終了いたしました。
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」、平成24年10月1日には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、市町村等においては虐待の防止、適切な対応、支援等の取り組みが求められています。北海道社会福祉士会は、年齢や分野、虐待種別に関わらず、権利擁護について改めて考え、虐待防止のための基本的な理解を深めることにより、実践現場における権利擁護意識の醸成と虐待防止法の円滑な施行に取り組み、関係機関職員の資質向上を目的とした研修会を開催いたします。
| 日時・会場 | 2017年8月26日(土)9:50~16:00(受付9:30~) 会場:かでる2.7 大会議室 (札幌市中央区北2条西7丁目) ※駐車場が限られていますので、公共交通機関をご利用ください。 |
|---|---|
| 定 員 | 150名(定員になり次第締切。初めて受講する方・会員を優先します。ご了承ください。) |
| 対象者 | (1)道各振興局社会福祉課虐待防止担当職員、市町村高齢者虐待防止担当職員
(2)市町村障がい者虐待防止担当職員
(3)以下の施設において勤務している職員
|
| 受講費 | 会員:3,000円 非会員:5,000円(食事・宿泊費・旅費は含みません) *社会福祉士会へ入会手続中の方は、会員扱いとさせていただきます。 |
| 申込期間 | 2017年7月18日(火)~7月25日(火) 申込受付期間外のお申込は受け付けられませんので、必ず上記期間内にお申込ください。 |
| 申込方法 | ①所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送でお申し込みください。 ②受講定員を超えた場合は、初めて受講される方・会員を優先し受講者を決定いたします。 |
| 受講可否の通知 | 受講決定者には8月上旬までに文書にて受講費の納入方法等についてご案内します。 |
2017年度地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修
更新日付:2017.05.24
地域包括支援センターの主要な業務の一つとして、ネットワーク構築業務があります。地域における生活支援を進めるにあたっては、当事者、家族、地域住民、民生委員、専門職、行政等、地域の関係者とのネットワークを構築することになりますが、その組織化自体に目的があるのではなく、「地域を基盤としたソーシャルワークを展開するためのネットワーク構築・活用」という視点が重要となります。
そこで、北海道社会福祉士会では、地域包括支援センター職員や関係者の方々が、地域を基盤とするソーシャルワーク実践をおこなうために必要となるネットワーク構築・活用のスキルを習得すること目的に研修会を開催します。
| 日程 | 前期:2017年7月8日(土)~7月9日(日) 後期:2017年10月22日(日) |
|---|---|
| 会場 | かでる2.7(札幌市中央区北2条西7丁目) |
| 受講要件 | (1)(2)のすべてを満たす方 (1)カリキュラムの全課程を出席できる方 (2)事前課題、中間課題を提出できる方 |
| 対象者 | ・地域包括支援センター(サブセンター・ブランチ含む)職員、市町村職員、 ・社会福祉協議会職員等地域を基盤としたソーシャルワークを実践している方 ・居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員等地域での活動を期待されている専門職の方 *演習等は地域包括支援センターの事例を使う予定ですが、市町村職員、社会福祉協議会職員の方もぜひご参加ください。 |
| 定員 | 30名(先着順) |
| 受講費 | 社会福祉士会会員:20,000円 会員以外:30,000円 ※社会福祉士会会員には入会手続中の方も含みます。 ※受講費には、全日程の資料代を含みます。食費・宿泊費・旅費は含みません。 |
| 宿泊・昼食 | 各自手配をお願いします。 |
| 申込方法 | 所定の「受講申込書」に必要事項を記入の上、FAXもしくは郵送にてお申し込みください。 (電話での申し込みは、受け付けておりません)。 |
| 申込期限 | 6月1日(木)~6月15日(木)まで(先着順) ※申込締切日前でも定員となり次第、締め切ります。 |
| 受講可否の通知 | 受講可否は6月22日(木)頃文書によりご連絡します。 *あわせて、事前課題、会場案内、受講費の納入方法、キャンセルの扱い等についてもご案内します。なお、受講申込者が少ない場合は、当研修を開催しない場合がありますので、予めご了承ください。 |
道央地区支部 会員サロン
更新日付:2017.05.24
こんにちは♪道央地区支部が開催する会員サロンをご案内します。
会員サロンは、会員等が定期的に集まり、資質向上、意見交換を行うことで社会福祉士としてのアイデンティティを確認するとともに、参加者が交流の機会を通じて、分野を超えたネックワークを広げることを目的にします。
今回のテーマは、「障がい者の就労支援」。皆さんの参加をお待ちしています。
| 日時 | 6 月23 日(金)18時30分~20 時の予定 |
|---|---|
| 会場 | 札幌市社会福祉総合センター「視聴覚室」4階 (札幌市中央区大通西19丁目地下鉄東西線「西 18 丁目」下車徒歩 5 分) |
| テーマ | 「障がい者就労支援の現状と展望 ‐寄せられる相談と社会福祉士への期待‐」 |
| 講師 | 北海道障害者職業センター 主任障害者職業カウンセラー 小池 磨美氏 |
| 参加費 | 本会会員は無料。非会員は 500 円(当日、受付にていただきます。) |
| 定員 | 50 名(早めにお申し込みください。) |
| 参加申込 | 6 月16 日(金)までにFAX(011-688-6878)にて 参加申込書をご送付ください。 |