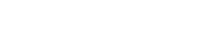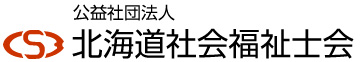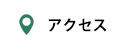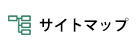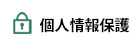トピックス
お知らせ一覧
年末年始業務について
更新日付:2025.12.08
本会事務局の年末年始業務について、下記のとおりお知らせいたします。年末の業務⇒2025年12月26日(金)まで
(電話受付時間:16時30分まで)
年始の業務⇒2026年1月5日(月)から業務を開始いたします。
かわら版No.71発行のお知らせ
更新日付:2025.11.28
かわら版No.71(2025年11月号)を発行しましたのでお知らせします。《かわら版71号の内容》
・第2回全道会員交流会(全道社会福祉士のつどい)が大盛況
・新人社会福祉士の紹介(道南、釧根地区支部)
・ベテラン社会福祉士の視点(道北、日胆地区支部)
・地区支部からのお知らせ
・Break time~三択クイズ~
・数字で見る北海道社会福祉士会
年会費引落について
更新日付:2025.10.01
会員のみなさま2025年度年会費の引き落しについてお知らせいたします。
2025年4月28日に引落しができなかった方、2025年6月~9月にご入会の方
および2025年9月までに口座変更届をご提出された方につきましては
2025年10月27日(月)が引落日となります。
口座残高の確認をお願いいたします。
引落金額:15,140円(年会費15,000円+引落手数料140円)
かでる2.7の臨時休館に伴う事務局業務について
更新日付:2025.09.26
本会事務局が入居している道民活動センタービル(かでる2.7)が受変電設備改修工事のため臨時休館となります。それに伴い、事務局の電話受付時間等を以下の通り変更いたします。
1.期間
2025年9月17日(水)から2025年9月26日(金)まで
2.電話受付時間
午前9時から午後4時まで
3.成年後見等のご相談について
来所相談はお受けできません。
電話でのご相談は、上記電話受付時間内で対応いたします。
4.入会資料請求、会員情報の変更など
ホームページのフォームまたはメールでご連絡ください。
5.研修の事前課題の受理連絡について
課題を受理した旨のご連絡は、担当者が確認次第送信させていただきます。
(即日送信ができない場合がありますのでご了承下さい。)
【北海道のハンセン病問題に関する協議会】松丘保養園訪問について
更新日付:2025.09.24
本会も参画しております「北海道のハンセン病問題に関する協議会」から、松丘保養園への訪問について案内がありましたのでお知らせいたします。北海道のハンセン病問題に関する協議会では、本年、下記の予定で青森県の国立療養所松丘保養園訪問を計画しております。
申込締切:2025年10月10日(金)まで
| 訪問先 |
国立療養所 松丘保養園 (〒038-0003 青森県青森市大字石江字平山19番地) |
|---|---|
| 訪問内容 |
・道民会会員と交流会 (お茶飲み程度は可) ・園内見学(学芸員が対応) |
| 経費 | この訪問に係る旅費などは、全て自己負担です。 |
| 日程 | |
|---|---|
|
【1日目】 令和7年11月27日(木) |
14:30 松丘保養園正面玄関前で現地集合 福祉棟にて検温、来園受付 園長へ挨拶(園長挨拶の予定がない方は交流会会場へ) 14:45~道民会会員と交流会 ※お茶飲み程度は可 16:00~園内見学(学芸員が対応) アクセス:JR新青森駅から1.3km。路線バス(14:46発)若しくはタクシーを利用。 |
|
【2日目】 令和7年11月28日(金) |
9:30~自治会長へ挨拶 |
| 申込方法 | 参加を希望される方は、申込フォームからお申し込みください。 →→→参加申込フォーム |
かわら版No.70発行のお知らせ
更新日付:2025.08.28
かわら版No.70(2025年8月号)を発行しましたのでお知らせします。《かわら版70号の内容》
・新理事・新監事のご紹介
・新体制・委員会担当理事紹介
・新人社会福祉士の紹介(道央、日胆地区支部)
・ベテラン社会福祉士の視点(十勝、道南地区支部)
・地区支部からのお知らせ
・2025年度第2回全道社会福祉士のつどい(全道会員交流会)開催のお知らせ
ぱあとなあ名簿登録料の引き落としについて
更新日付:2025.08.01
ぱあとなあ北海道名簿登録者のみなさま2025年度の名簿登録料引き落とし日についてお知らせいたします。
2025年8月27日(水)に名簿登録料の引き落としを行いますので、
口座残高のご確認をお願いいたします。
引落金額:10,140円(名簿登録料10,000円+引落手数料140円)
【声明】 生活保護基準引き下げ訴訟に関する最高裁判決についての声明(JFSW)
更新日付:2025.07.10
日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)では、生活保護基準引き下げ訴訟に関する最高裁判決について、7月9日付で、以下の声明を発出しておりますので、情報共有させていただきます。■生活保護基準引き下げ訴訟に関する最高裁判決についての声明(JFSW)
https://jfsw.org/2025/07/09/4040/
年会費引落について
更新日付:2025.07.01
会員のみなさま2025年度年会費の引き落しについてお知らせいたします。
2025年4月28日に引落しができなかった方、2025年4月・5月にご入会の方
および2025年5月までに口座変更届をご提出された方につきましては
2025年7月28日(月)が引落日となります。
口座残高の確認をお願いいたします。
引落金額:15,140円(年会費15,000円+引落手数料140円)
懲戒処分の公表について
更新日付:2025.06.11
各位
北福士発 第25-055号
2025年6月11日
公益社団法人北海道社会福祉士会
会 長 出 町 勇 人
2025年6月11日
公益社団法人北海道社会福祉士会
会 長 出 町 勇 人
懲戒処分の公表について
本会は、会員の倫理の維持・向上を図ることを目的として、社会福祉士としての活動に対する苦情申立てが行われたときは、倫理委員会による調査を行い、社会福祉士の倫理綱領・行動規範に禁じられている行為を行ったと認められる場合に理事会において懲戒処分を決定します。
この度、2025年1月25日付け懲戒処分を決定しましたので、会員の倫理綱領遵守の自覚を促すとともに適正な実践を確保し再発防止に資すること等を目的として、下記のとおり公表します。
記
| 1 対象者 | |
| 本会会員のうち、社会福祉士の倫理綱領及び行動規範に違反が認められた者 | |
| 2 懲戒の種類 | |
| 戒告 | |
| 3 懲戒の事由 | |
| 対象者が、明らかに判断能力が低下している初対面のクライエントと財産管理や死後事務委任契約を締結させたことは、本人の意思を十分確認しないもので、倫理綱領(倫理基準Ⅰ-7、同Ⅳ-3)及び行動規範(Ⅰ-7-2、Ⅰ-7-3、Ⅳ-3-1、Ⅳ-3-2)に違反し、不適切である。 | |
| 4 懲戒処分年月日 | |
| 2025年1月25日 | |
| 5 公表方法 | |
| 本会一般ホームページの「お知らせ」 | |
| 6 公表期間 | |
| 1年間 | |
|
次の項目へ »