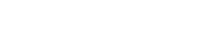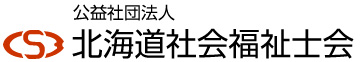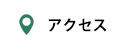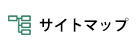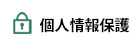トピックス
一般向け各種情報一覧
2016年度日本ソーシャルワーク学会第33回大会のご案内
更新日付:2016.04.19
| 1,大 会 名 | 日本ソーシャルワーク学会 2016年度 第33回大会 |
|---|---|
| 2,大会テーマ | 「ソーシャルワークの『グローカル』な展開をめざして」 |
| 3,日 時 | 2016年7月9日~10日の2日間 |
| 4,会 場 | 同志社大学 今出川キャンパス |
| 5,大会内容 | 基調講演、大会校企画シンポジウム、学会企画シンポジウム、自由研究報告等 |
大会についての詳細は日本ソーシャルワーク学会ホームページに掲載しております。
参加申込や自由研究発表申込のフォーマットもダウンロードできるようになっております。
» 日本ソーシャルワーク学会ホームページ
会員のみなさまにお知らせ
更新日付:2016.03.31
年会費の引落について
年会費の引き落としは、2016年度から4月27日となります。 口座の残高の確認をお願いいたします。変更届について
異動の時期になりました。 自宅・勤務先等変更がございましたら本会への届出もお忘れなくお願いいたします。生活困難者支援委員会通信~vol.3
更新日付:2016.03.07
北海道社会福祉士会生活困難者支援委員会(以下、委員会)から、3回目の通信をお届けします。
詳細は下記リンクをクリックし、PDFにてご確認ください
 生活困難者支援委員会通信
生活困難者支援委員会通信
司法と福祉の特別委員 ニュースレターVol. 02
更新日付:2016.03.07
司法分野との連携特別委員会の通信2をお届けします
詳細は下記リンクをクリックし、PDFにてご確認ください
 司法と福祉の特別委員 ニュースレターVol.02
司法と福祉の特別委員 ニュースレターVol.02
公益社団法人北海道社会福祉士会実践研究集会(全道大会)
更新日付:2016.03.07
2016年度より標記実践研究集会(全道大会)を開催いたします。
本会として魅力ある組織作りの一環として、本会独自に社会福祉士の実践研究大会を開催し、会員の資質の向上と交流の機会として実施するものです。
現在、企画総務委員会にて企画・開催準備を進めております。具体的な内容につきましては、決定次第、ホームページ等でお知らせいたします。記念すべき初めての集会となりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
さて、当該集会では会員等(個人・グループ・地区支部等)の実践発表を実施いたしますので、会員等の発表者(実践発表・ポスター発表)を募集いたします。
つきましては、別添申込要領によりお申し込み下さい。(なお、募集多数の場合には発表分野等により担当委員会等にて選考させていただく場合があります。)
| と き | 2016年6月11日(土曜日) 9:45~17:30(受付9:00) |
|---|---|
| ところ | 道民活動センター かでる2.7 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 |
| 主 催 | 公益社団法人北海道社会福祉士会 |
| 参加費 | 会員4,000円(非会員8,000円)※変更になる場合もあります。 |
地域包括ケア講演会
更新日付:2016.03.01
個別支援と地域支援の相関性
| 日時 | 平成28年5月28日(土) 14:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 道東経済センタービル5階 大会議室 釧路市大町1-1-1 |
| 対象 | 一般市民・医療・介護関係職種 |
| 申込 | 申込書によりお申し込みください。 |
| 費用 | 会員無料/非会員1,000円 お近くの有料駐車場または公共交通機関をご利用ください。 |
詳細・申込用紙は下記リンクをクリックし、PDFにてご確認ください。
 研修会のご案内
研修会のご案内
「介護悲劇」は繰り返させない! 市民学習会
更新日付:2016.02.26
昨年2月に札幌市で「介護疲れによる殺人」が起き、私たちに大きな衝撃を与えました。介護保険制度が発足して15年経つのに、全国的にこうした介護の悲劇があとを絶ちません。制度のことを学び、悲劇を繰り返さないため、いっしょに考えましょう!
どなたでも参加できます。多数おいで下さい!
| 日 時 | 2016年3月5日(土)13:00~15:45 |
|---|---|
| 会 場 | 市民ギャラリー内 中央区東地区会館(南2東6)TEL 011-241-1696 |
詳細は下記リンクをクリックし、PDFにてご確認ください
 「介護悲劇を繰り返させない」市民学習会
「介護悲劇を繰り返させない」市民学習会
主催者から、前回掲載した内容に誤りがあったとの連絡がありましたので再掲載いたします。
訂正箇所:開始時間、電話番号
司法との連携学習会
更新日付:2016.02.05
北海道社会福祉士会は、2014 年度、高齢者や知的障がい者等の福祉的支援を要する「被疑者・被告人段階」の支援について、日本弁護士連合会をはじめとする司法関係機関との連携のもと、司法分野における社会福祉士の関与のあり方に関する連携スキームを検討するための調査研究事業(日本社会福祉士会実施)に協力しました。
この事業は、逮捕時、裁判段階等において、弁護士等との連携のもと、福祉的支援を必要とする高齢者・障がい者等に対し、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士が関与し、「接見」「アセスメント」「更生支援計画の作成」「居住環境の調整」「福祉・医療サービスの利用調整」等の実践を、都市部(札幌、横浜、大阪)でモデル的に実施しました。
すでに道内においても、個別案件として弁護士等と社会福祉士との間で「被疑者・被告人段階」の方への「入口支援」を行っている事例やその他の部分での実践もありますが、今後社会福祉士への期待が高まる中、適切に連携していくためには持続可能な司法と福祉の連携の仕組みを会として構築していかないとなりません。
そこで、このたび、基調講演や道内における司法・福祉の連携実践報告を受け、今後道内において一層円滑に連携が進むことを目指した学習会を開催します。
| 開催日 | 2016年3月13日(日) 9:30~11:45 |
|---|---|
| 会場 | かでる2・7 10階 1030会議室 (〒060-0002札幌市中央区北 2 条西 7 丁目1) |
| 参加対象 | 社会福祉士、弁護士等 |
| 定員 | 30名 |
| 参加費 | 無料 |
| 申込方法 | 所定の申込書にてFAXまたは郵便等によりお申し込みください。 |
| 申込締切 | 2016年3月3日(木)まで(先着順) ※申込締切日前でも定員となり次第締め切ります。 |
| 参加可否 | 定員超過により参加できない場合のみ申込書記載の連絡先に連絡します。 |
第14回高齢者障害者の権利擁護セミナー
更新日付:2016.02.03
謹啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、当団体の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今年も「高齢者障害者の権利擁護セミナー」を、次の開催要項のとおり開催することになりました。
今回のセミナーにおいては、「誰もが暮らしやすい地域を目指して」をテーマとし、障害者差別解消法の施行を見据えた内容として、制度説明やパネルディスカッション等を行うこととします。
つきましては、時節柄ご多忙のこととは存じますが、皆様お誘いあわせの上是非ご参加いただきたく、ご案内いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
敬具
| 日 時 | 平成28年 2月13日(土)13:30~17:00(13:00~受付) |
|---|---|
| 会 場 | 旭川市大雪クリスタルホール 大会議室 (旭川市神楽3条7丁目) |
| 参加対象 | 関係団体会員、成年後見制度や高齢者・障害者の権利擁護に携わっている方及び関心のある方 |
| 定 員 | 180名 |
| 参 加 費 | 〔セミナー〕 無 料 〔懇 親 会〕 3,500円程度 (当日受付にてお支払いください) ※関係団体会員等で希望者のみ。セミナー終了後実施します。会場は当日ご案内いたします。 |
| 申し込み | 申し込み先 社会福祉法人かがやき 法人本部事務局 070-0028 旭川市東8条2丁目3番11号 電話(0166)22-4000 FAX(0166)22-2345 申し込み方法 2月8日(月)までに、郵送又はFAXにて参加申込書を上記申し込み先まで送付の上、お申し込み ください(事前にお申し込みください)。 |
2015年度(第18回) 北海道ブロック現場実習実践研究セミナー 実習指導者フォローアップ研修
更新日付:2016.02.02
実践倫理を基盤に置くスーパービジョン
実践における価値・倫理の理論整理と価値・倫理を基盤としたスーパービジョンの検討を通して
実践力がある社会福祉士養成において、実習指導者は、実習学生に一定の責任・義務、権利を保持させつつ、現場の実践コミュニティに参加する機会を創出することが重要である。この機会を通して学生は、クライエント・システムに対して直接的・間接的に関わり、さらに、実習指導者や職員が利用者に関わっている状況を観察し、また記録の記載、閲覧や職員からの講義等を通して現場のソーシャルワーク実践を経験することになる。スーパービジョンでは、これらの機会での実習経験を対象化し、客観的に吟味・分析し、脈絡付けをすることで省察が行われる。この実習経験の検討の方向性の基盤の一つとなるのが価値・倫理の視点である。 ここで求められるスーパーバイザーである実習指導者像は、現場の実践における価値・倫理の理論的整理ができ、さらに専門性の要素である価値・知識・技術の関係的理解ができることである。これに基づいて、価値・倫理を基盤に置いたスーパービジョンを展開することが出来る能力を涵養することが今回のテーマである。この背景には、所属する施設・機関の中に利用者に対して権利擁護システムを確立していることが要求される。 なお、北海道ブロックで標準化されている実習評価表の項目においても、「社会福祉専門職の価値・倫理について学ぶ」(中項目)、「社会福祉士の業務の中から、社会福祉士の価値・倫理判断に基づく行為を発見抽出して説明することができる」(小項目)、「人格・人権を尊重した関わりができる」(小項目)、「倫理的(価値)ディレンマの具体例を挙げることができる」(小項目)等が列挙され、重要な実習到達目標になっている。 本研修では、実践倫理を基盤に置くスーパービジョンに焦点を当てて、「実践における価値・倫理」の理論を明確にしつつ、実際に行なわれている「価値・倫理を基盤に置くスーパービジョン」に触れ、今後の実習スーパービジョンの質的向上に貢献できることを目的に展開されます。| 主 催 | 公益社団法人北海道社会福祉士会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 時 | 2016年3月12日(土) 10:00~16:00(9:30受付開始) | ||||||
| 会 場 | 学校法人西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校3階 講堂 (札幌市中央区南5条西11丁目1289-5 石山通・国道230線沿い) | ||||||
| 参加定員 | 社会福祉士実習指導者講習会を修了認定された方、相談援助実習を指導担当されている方及び今後予定されている方、養成校教員及び学生。 | ||||||
| 参 加 定 員 | 60名 | ||||||
| 参 加 費 | 会員:2,000円 非会員:3,000円 学生:無料 | ||||||
| 振 込 先 |
|
||||||
| 締め切り | 2016年2月29日(月) |
詳細(研修プログラム)・お申込用紙は、下記リンクをクリックし、PDFにてご確認ください
 【要綱】2015年度 第18回北海道ブロック現場実習実践研究セミナー実習指導者フォローアップ研修
【要綱】2015年度 第18回北海道ブロック現場実習実践研究セミナー実習指導者フォローアップ研修