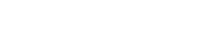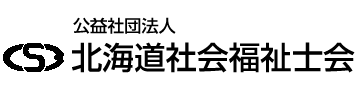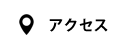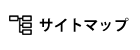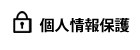トピックス
一般向け各種情報一覧
【道央地区支部】権利擁護・司法福祉セミナーのご案内
更新日付:2020.09.11
道央地区支部では、下記の通り「権利擁護・司法福祉セミナー」を開催します。
【日 時】 2020年11月21日(土)
【会 場】 札幌市社会福祉総合センター4階「視聴覚室」
(札幌市中央区大通西19丁目 地下鉄東西線「西18丁目」下車徒歩3分)
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
2020年「社会福祉士全国統一模擬試験」のお知らせ
更新日付:2020.09.09
申込は締め切りました
本模擬試験は、自宅受験や団体受験など複数の受験方法を選択することができます。 ご自身の学習状況や当日の試験の実施方法やマークシートの記入方法を確認するなど試験当日の雰囲気を確認し、受験勉強を始める動機づけに役立てることもできます。 また、集合受験では、会場を選択することができ、本会の模擬試験の特徴となっております。 詳細・申込用紙は下記リンクをクリックし、PDFにてご確認ください【事後課題様式】障がい者の地域生活支援研修を受講の皆さま
更新日付:2020.09.06
障がい者の地域生活支援研修を受講の皆さま向けに、事後課題の様式を掲載いたします。
下記よりダウンロードし、ご活用ください。
【事前課題様式】2020年度成年後見人材育成研修を受講されるみなさまへ
更新日付:2020.08.31
2020年度成年後見人材育成研修を受講される皆様向けに、事前課題の様式を掲載いたします。
下記よりダウンロードし、ご利用ください。
※掲載が遅くなり申し訳ございませんでした。
2020年度成年後見人材育成研修の受講にあたって
更新日付:2020.08.26
新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施を検討しておりましたが、先般お送りしました日程の通り開催致します。
「参加確認書」は、ホームページから送信する事もできます。
なお、開催にあたり本会の方針に基づき、集合研修は行わず、インターネット回線を使用したオンライン研修(クラウド型WEB会議システム「ZOOM」の利用を予定しておりますので、あらかじめご承知おき願います。)
※特に、URLをお送りするメールアドレスに誤りがあると当日受講できなくなります。
十分確認してご入力下さい。
参加確認書はこちらから入力できます。
研修を受講申し込みされる方へ【お願い】
更新日付:2020.08.26
研修申込や受講確認をFAXでお送りいただく方へお願いです。
事務局からのご案内に「空メールをお送り下さい」と記載しておりますが、メールをお送りいただく際に「お名前」「申込された研修の名称」をお書き添え下さい。
今後は、ホームページ上でお申し込みが可能な形に順次対処しており、しばらくの間ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
令和2年7月豪雨災害に伴う被災地活動支援金募集について
更新日付:2020.07.28
このたびの令和2年7月豪雨により、犠牲になられた方々とご遺族の皆さまに謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災した方々に心よりお見舞い申し上げます。また、行方不明となっておられます方々の早期発見を願うと共に、一刻も早い復旧を願っております。
今回の豪雨災害に対して、日本社会福祉士会では災害対策本部を設置し、被災圏域の県社会福祉士会の活動や被災した県社会福祉士会の活動等を支援するための募金を開始しました。
つきましては、下記リンクより詳細をご覧いただきたくご案内いたします。
【日本社会福祉士会・令和2年7月豪雨・支援金の募集について URL】
https://www.jacsw.or.jp/15_TopLinks/SaigaiTaisaku/2020KyushuOame/kifu.html
ぱあとなあ名簿登録料の引き落としについて
更新日付:2020.07.21
ぱあとなあ北海道名簿登録者のみなさま
2020年度の名簿登録料引き落とし時期についてお知らせいたします。
8月27日(木)に名簿登録料(10,140円)の引き落としを行いますので、口座残高のご確認をお願いいたします。
【日程案内】成年後見人材育成研修・ぱあとなあ北海道名簿登録研修について
更新日付:2020.07.10
2020年度 成年後見人材育成研修(委託研修)とぱあとなあ北海道名簿登録研修の日程が確定いたしましたのでお知らせいたします。
<成年後見人材育成研修>
前期 2020年10月31日(土)
2020年11月1日(日)
後期 2021年1月9日(土)
2021年1月10日(日)
<ぱあとなあ北海道名簿登録研修>
2021年1月11日(月・祝)
詳細については会員用ページに掲載の開催要項をご覧ください。
◇◆◇パスワードをお忘れの会員の方へ◇◆◇
更新日付:2020.07.08
パスワードを忘れてしまい、次のようなことで不便を感じている方へ・・・
◎会員専用のページが見られない
◎メールマガジンの登録ができない
◎けど、電話でパスワード聞くのはちょっと・・・
ログインしなくても問い合わせが可能ですのでお知らせします。
1,ホームページの下側「お問い合わせ」から本会事務局へお問い合わせいただく
2,本会(info@hokkaido-csw.or.jp)へメールでお問い合わせいただく
いずれかの方法で可能ですので、ぜひご連絡下さい!